「親から市街化調整区域の土地を相続したけど、どう活用すればいいの?」
「売ることも家を建てることもできないって本当?」
都市計画法で開発が制限されている市街化調整区域は、宅地と同じ感覚で相続すると、思わぬ落とし穴があります。
しかし、正しい測量・法規制の確認・相続判断をすれば、無理なく活用する道も見えてきます。
今回は、土地家屋調査士かつ相続診断士の立場から、
市街化調整区域の土地について、「境界」「法規制」「相続判断」の3つの視点で詳しく解説します。
① 境界が不明確なままだと、活用も売却もできない
市街化調整区域に多いのが、古くからの農地・山林などで境界があいまいな土地です。
土地を活用するには、まず正確な測量と隣地所有者との境界確定が必要です。
✅ 接道が里道・水路の場合は「払下げ手続き」も必要
✅ 土地が広い場合は「分筆」して一部売却も検討可能
② 「市街化調整区域」でも建築できるケースがある
一般的に市街化調整区域は「原則として開発できない」とされますが、
次のような例外や緩和措置があります。
• 既存宅地要件:昭和45年以前からの住宅地等であれば建築可
• 農家住宅や地域住民向けの施設などは申請により建築可
• 用途変更や農地転用許可によって事業活用できることも
こうした制度は、地域や市町村によってルールが異なるため、個別確認が不可欠です。
③ 相続判断は「感情+コスト+将来性」で考える
市街化調整区域の土地は、将来的にも利用制限が続く可能性があります。
そのため、固定資産税や維持管理のコストと、将来の相続人への影響も踏まえた判断が必要です。
✅ 相続放棄や共有整理の検討も視野に
✅ 売却できなくても、「隣地との合筆」や「一部活用」で負担を減らすことも可能
【土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直コメント】
市街化調整区域の土地は、「使えない土地」ではなく、「扱い方が難しい、行政の規制が多い土地」です。 私は相続診断士として、「引き継ぐか、手放すか」だけでなく、「どう残すか」という選択肢も含めて、ご家族の想いと財産のバランスを踏まえたご提案を行っています。
特に地方に多いこのような土地こそ、測量・境界・規制の把握をもとに、早期のご相談をおすすめします。
【まとめ】
• 市街化調整区域の土地は、境界・接道条件を整えることで活用可能性が広がる
• 法規制を調べれば、建築や転用が認められるケースもある
• 相続判断は「持ち続けるコスト」と「将来のトラブル回避」を天秤にかけて検討を
【相談無料】相続・不動産のことでお困りでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。
👉無料相談はこちら
連絡先や相談案内(連絡先・住所・電話番号・メールアドレス)
〒520-0232滋賀県大津市真野2丁目2番44号
相続と未登記建物の専門家
土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直
💬 LINE公式アカウントからも簡単にご相談いただけます
📘今だけ!相続でお困りの方に「相続3点セット」無料プレゼント中【LINE登録者限定】
「まだ登記していない家があるけど、今すぐ動くべき?」など、気軽に質問OK。
まずは気軽に登録してみてください。
✔ 相続って何から始めればいい?
✔ 手続きが遅れると損するって本当?
✔ 登記してないけど問題ある?
匿名での相談も可能です。
そんな方のために、相続の“最初の一歩”をサポートする
✅ 相続3点セット(無料PDF) をご用意しました!
▶︎ 友だち追加はこちら
📲 スマホの方はこちらのQRコードを読み取ってください

📞 お電話でのお問い合わせ:077-532-3172
📩メールでのお問い合わせ:office.mano2.2.44@gmail.com
📍対応エリア:大津市・草津市・守山市・栗東市・高島市・近江八幡市ほか滋賀県全域対応
🏢未登記建物・相続登記・火災保険リスク対策のご相談は、
土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直(滋賀県大津市)まで。
🌐 詳しくは公式サイトをご覧ください → https://sokuryou-touki.com
🏠 HPトップページへ
👉 ご相談・お問い合わせは、竹内貞直 土地家屋調査士・相続診断士事務所のトップページへどうぞ。
📍 地域の皆様へ
👉 「滋賀県大津市を始め、守山市、野洲市、草津市、栗東市、近江八幡市、彦根市、東近江市、甲賀市、高島市、長浜市、米原市、八日市市など周辺で、土地・建物の相続や名義変更にお困りの方へ」
📘 「相続診断士とは」
👉 「相続診断士は、円満な相続を実現するために早期の課題発見と対策を提案する専門家です。初回相談無料で対応しております。」
「未登記建物とは?」
所有者が不明確で、相続や売却の際にトラブルの原因となります。
土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。
🌿相続・登記のご相談は、滋賀県大津市の土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直まで。
「祖父名義のまま」「未登記のまま」「建物を壊したのに登記が残っている」など、
どんな小さな疑問でも丁寧に対応します。
まずは公式LINEまたはお電話で、お気軽にご相談ください。
📚 参考リンク(公式情報)
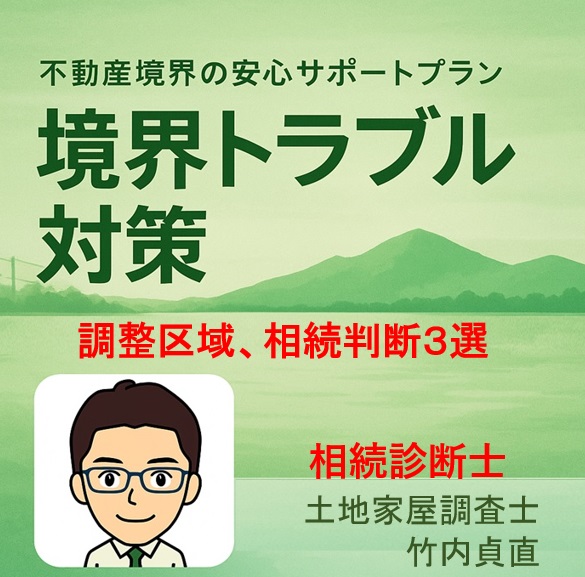
コメントを残す